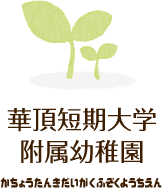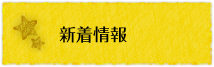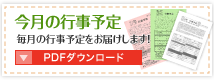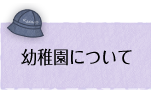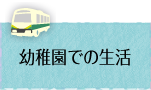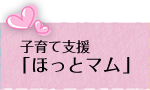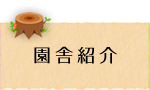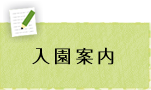2020年02月03日
節分会をしました。
日本に『お化け』と言って節分の日に仮装する風習があることをご存じですか?仮装と言えば、ハロウィンを連想される方が多いと思いますし、また、祇園など京都の花街では今も「おばけ」の風習が残っているので、それをご存じの方は「『お化け』は舞子さんや芸子さんが仮装すること」と思っておられる方もおられるかもしれません。
実は、この「おばけ」という節分の仮装の風習は京都を中心として江戸時代末期から昭和初期に盛んにおこなわれていたそうです。しかも、単に仮装して楽しむのとは違って大事な意味のある事だったようです。
そこで今回も昨年に引き続き、いつもの節分豆まきの行事に京都の風習を少し取り入れて、子どもたちに「節分お化け」を体験させたいと思い計画しました。みんなで変装し邪気を払います。
|
節分お化け(せつぶんおばけ)、あるいは単にお化け、オバケとは、節分の夜(立春前夜)の厄祓い(厄除け)として行われる日本の儀式。普段と違う服装で、社寺参拝を行う異装儀式である。 概要:節分の夜に、老婆が少女の髪型である桃割にしたり、逆に少女が成人女性の髪型である島田に髪を結ったりする。このため「オバケ」とは「お化髪」が語源であるという説もある。また異性装も行われる。そしてこのような異装のまま、寺社へ詣でて新年の平穏を祈ることも行われる。 このような異装を行うのは、違う年齢や違う性など「普段と違う姿」をすることによって、節分の夜に跋扈するとされる鬼をやり過ごすためである。 立春前夜は、暗い季節(秋・冬)と明るい季節(春・夏)の変わり目である。 また旧暦では年の変わり目である1月の始まりもおおよそこの頃であり、方位神が居場所を変えるなど、古い年から新しい年へと世界の秩序が大きく改組される不安定な時季と信じられた。 この様な時季には現世と異世界を隔てる秩序も流動化し、年神のような福をもたらす存在が異世界からやってくる反面、鬼などの危害をもたらす存在もやってくるとされた。そこで豆まきなどの追儺儀式が行われるが、お化けもまたそうした儀式のひとつである。 |

変装して知恩院にお参りにいきました。

鬼に気づかれないようにみんな神妙でした。

お家の方がいろいろと工夫してくださり、子どもたちは大喜びで見せてくれました。